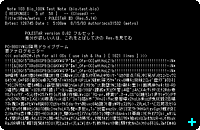PC-9801シリーズはNECから発売された独自アーキテクチャのパーソナルコンピューターで、前述の通りBio_100%のメインプラットフォームとなっていたハードである。1982年には世に登場していたが、1980年代終盤までは8bit機のPC-8801シリーズを始め、富士通のFM-7、シャープのX1などがホビーユースとしての地位を確立していたため、元々ビジネスユースとして位置づけられていたPC-9801シリーズがホビーユースとして陽の目を見たのは、1980年代後期から1990年代初期のこととなる。
元々PC-8801シリーズもビジネスユースとして発売されていたが、1985年に登場したPC-8801mkⅡSRを以てホビーユースに方向転換。640×200ラインというグラフィック解像度は従来モデルと変わらぬものの、発色数の強化を図りつつ、スクロール機能やFM音源チップも搭載され、ビジネス機としての面影は跡形もなく消え去った。しかしながら時代の流れには逆らうことができず、ニーズに応えられなくなった8bit機たちは1980年代終盤にその役目を終えている。
一方PC-9801シリーズは、PC-8801シリーズ全盛期の裏でハイエンドのビジネス機として着実に進化を遂げ続けていた。発売当初は8086プロセッサーを搭載した16bit機であったが、CPUの進化に伴う形で80386プロセッサーを搭載した32bit機も登場し、飛躍的に処理能力を向上させている。それに加えて640×400ラインというPC-8801シリーズの倍のグラフィック解像度を備えていることもあり、PC-9801シリーズはビジネス機の枠にとどまることなく、PC-8801シリーズに代わるホビーユース機として脚光を浴びることとなった。1985年に発売されたPC-9801VMからは、従来モデルよりも発色数が増え、さらにGRCG(グラフィックチャージャー)と呼ばれる機能の追加により裏画面処理が可能になるなど、まさにゲーム向けのマイナーチェンジが施されている。Bio_100%の作品にも「PC-9801VM以降対応」のものが多く見られるが、これはそのGRCGを活用していたからに他ならない。こうした機能強化によって一気にホビーユースの需要が高まったことは言うまでもなく、1990年以降のモデルにはFM音源チップも標準搭載されるようになり、PC-9801シリーズはビジネスとホビーの両面を支えるハードとして一時代を築き上げた。
しかしながら、海外において標準プラットフォームとなりつつあったIBM PC/ATおよびその互換機の上陸によって、PC-9801シリーズはその足元を大きく揺るがされてしまう。IBM-PCのコストパフォーマンスもさることながら、1990年代半ばにはオペレーティングシステムがMS-DOSからWindowsへと移行していき、ユーザー側が独自アーキテクチャにこだわる理由がなくなってしまったのである。IBM-PCに対抗すべく、同等の性能を備えたPC-9821シリーズも発売されたが、もはやその勢いを取り戻すことはできず、日本のビジネスとホビー市場の中心にあったPC-9801シリーズは、1990年代終盤にその使命を終えたのだった。
Windowsが一般に普及する以前、PC-9801シリーズはMS-DOSと呼ばれるオペレーティングシステムでコントロールされていた。コマンド入力によってファイルやディスクの管理、プログラムの起動などを行うものであり、現在でもWindowsのスタートメニューからアクセサリ→コマンドプロンプトを選択することによってその面影を見ることができる。MS-DOSの知識がない方はヘタにいじらないほうが無難だが、このような黒地に白文字の地味な画面がパーソナルコンピューターのデフォルトだった時代もあったのだということを知っておいていただければと思う。
その後、MS-DOSでの基本的な操作がグラフィカルかつマルチタスクに行えるようになったWindows3.0が1991年に、そしてさらに安定性を増したWindows3.1が1993年に登場。しかしながらこの時点ではまだMS-DOSの勢力が根強く残っていたため、PC-9801用のソフトウェアとWindows用のソフトウェアが市場やネット上に混在する状況が続いていた。特にゲームに関しては、MS-DOSよりもWindowsのほうがグラフィック処理の負荷が高くなってしまうという問題があり、当時の開発者たちを大いに悩ませた。これに対してマイクロソフトは、高速描画を可能とする「WinG」なるグラフィックライブラリを開発し、状況の改善に努めている。そしてMS-DOSの呪縛から解き放たれ、オペレーティングシステムが完全に切り替わりを見せたのは、1995年にWindows95が登場してからのこととなる。同時期にはWinGに代わるライブラリ群として「DirectX」も開発され、ゲームに関してもまったく問題なくWindows上でプレイできる環境が整えられた。
Bio_100%の作品も、1991年の発足から数年はPC-9801シリーズのMS-DOS上で動かすことを前提としていたが、混沌とした状況を逆手にとるようにWinGやDirectXをいち早く取り入れ、意欲的にWindows用の作品の開発にも着手している。またPC-9801だけでなく、独自技術によってIBM PC/ATおよびその互換機のDOS上で動作する作品の開発を行っていたことも、記憶にとどめておきたい。
日本で現在のようなインターネットのインフラが確立されたのはほんの数年前の話である。今でこそ容易に世界中のサイトにアクセスすることが可能となり、動画や音声によるコミュニケーションも当然となりつつあるが、ほんの十数年前まではそれも夢物語であった。
ではインターネットが普及する以前はどのようなオンラインコミュニケーションが図られていたのかというと、1980年代中盤から「パソコン通信」と呼ばれるネットワークが広がり始め、電子掲示板を中心に、電子メールの送受信やチャットなど、文字データによる情報のやりとりが活発に行われるようになる。
パソコン通信は、通常の電話回線からモデムを介し、企業や一個人が立ち上げたホスト局にダイヤルアップ接続して利用する形態となっていたため、インターネットのようにユーザー同士が並列でつながるワールドワイドなネットワークではなく、そのホスト局に接続したユーザー同士のみがコミュニケーションを図れるという、ある意味クローズドなネットワークとなっていた。だが、三人寄れば文殊の知恵という言葉もある通り、見ず知らずの人たちが集ってコミュニケーションを図るという行為は、当時からすればなによりも刺激的だったに違いない。パソコン通信サービスの大手としてはASCIInet、NIFTY-Serve、PC-VANなどが代表的なところであるが、全盛期にはこれらのホスト局の接続者数も数十万~百万人超に及び、様々な情報を求めるユーザーたちで賑わい、クローズドであることを感じさせない程の盛り上がりを見せていた。
こうしてパソコン通信が普及するに連れ、自作のプログラムをネットワーク上で公開するユーザーも現れた。ツールであれば使いやすさを重視し、ゲームであれば単純におもしろさを追求する作品が多く見られ、商用ソフトウェアより支持を集めていたものも少なくない。これが今でいうところのオンラインソフトウェアの始まりであり、こうした流れの中でBio_100%も誕生したのだった。
オンラインソフトウェアにはいくつかの区分があり、無料で使用できる「フリーウェア」と、試用期間を経た後に使用料を支払わなければならない「シェアウェア」の2種類が一般的となっており、どちらも著作権は作者個人または団体に帰属する。かつては、作者が著作権を放棄した上でプログラムを配布するPDS(パブリックドメインソフトウェア)と呼ばれる区分も存在したが、日本の法律上(著作権法59条著作者人格権)では完全なる著作権放棄が成立しないため、現在の日本においてはこの呼称が使われることはない。
Bio_100%の作品もフリーウェアおよびシェアウェアとして公開されてきたが、当時はこうしたオンラインソフトウェアの制作に多人数で着手するということは稀であった。自作ゲームといえば個人での制作が一般的だったため、そのクオリティーには自ずと限界が生じていたものだが、そんな時代に固定観念を突き破ってみせたBio_100%のスタイルは周囲に多大な影響を及ぼし、それと同時に自作ゲーム全般のクオリティーを飛躍的に向上させるためのトリガーになっていたともいえるだろう。